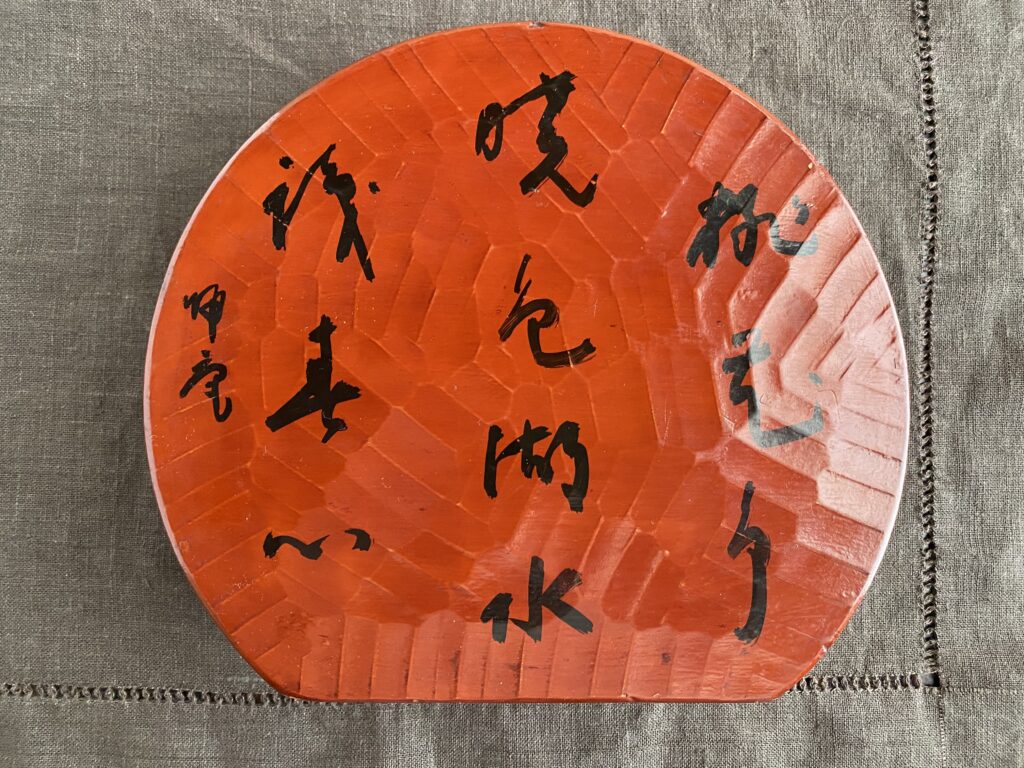No.124 洋風肉じゃが

今が旬のエンドウ豆を沢山いただいた。友人のご実家が家庭菜園で収穫したものだ。今までにも胡瓜や馬鈴薯、玉葱など色々頂いた事があるが、どれも美味しく素人とは思えない出来栄えで驚く。今回はこのスナップエンドウの他に、絹さやをいただいた。どちらも私の好物。ちょうど新じゃがと新玉葱が有るので、スナップエンドウを使って洋風の肉じゃがを作る事にした。春野菜は甘くて香りが良いから、味付けは甘味を加えずにシンプルにしたかった。精肉ではなくてベーコンを使う事で、燻製された脂と香りがコクを増す。市販のブイヨンを少し使って、小さいローリエの葉を一緒に煮込み、塩味で仕上げた。
器は古染付で、見込みの中央にだけ模様が描かれている、ほぼ真っ白の白磁の鉢。しかし、よく見ると内側に陰刻で幾何学的な模様が彫られている。鉢の口に近い上の部分は生地も薄いため、陰刻は自然に消えているけれど、胴の辺りには少し青みがかった釉薬が僅かな陰刻の模様を浮かび上がらせている。口の部分だけもう一回り開いている輪花の縁は、当時の良質ではない釉薬のせいで爆ぜてしまって虫食いだらけ。でも、それがこの白い鉢にいっそうの古染らしさと風情を加えている。

器 古染付鉢 径15,5cm 高9,5cm